COLUMN
採用広報の始め方|攻めの採用戦略で採用難を乗り越える方法
2025.5.26
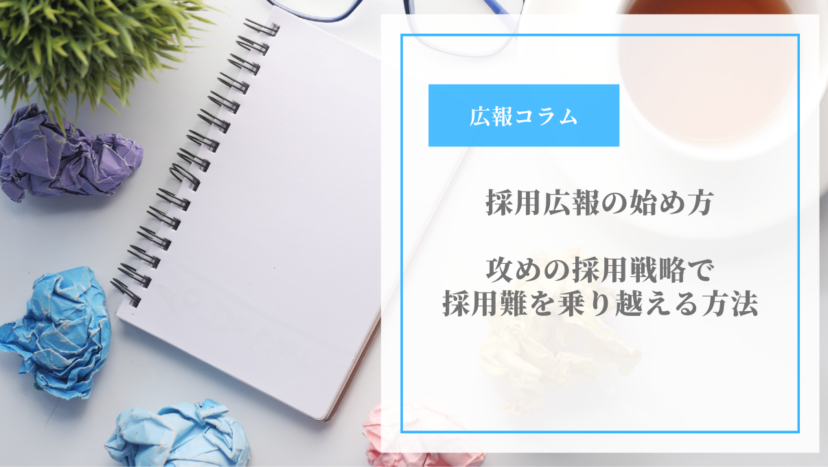
なぜ今「採用広報」が求められているのか?多くの企業が頭を抱えているのが「採用がうまくいかない」「母集団が集まらない」という課題です。少し前までは、求人広告を出せばある程度の応募が見込めた時代もありました。でも今は違います。 まず背景にあるのは、採用市場の大きな変化です。日本は超高齢化社会に突入し、若年層の労働人口が年々減少しています。つまり「これ以上働き手が増えることはない」——この現実を直視せざるを得ません。 そしてもう一つの変化、それが採用手法の多様化です。SNSの普及、情報収集方法の変化により、求職者は企業の採用サイトだけでなく、SNS、口コミ、社員の声など、あらゆるメディアから情報を得ています。 かつてのように「採用広告を出して待つ」だけの時代は終わり、潜在層へ向けた情報発信の重要性が格段に高まっています。企業は、求職者がまだ「転職しようかな」と考え始める前から、自社を認知してもらい、関心を持ってもらう必要があるのです。 そんな時代に求められるのが「採用広報」。これは、いわば“攻めの採用戦略”。本記事では、採用広報をこれから始めたい企業に向けて、基礎から実践方法までをわかりやすく解説していきます。
目次
1. 採用広報を始める前に考えるべきこと
「採用広報って何から始めたらいいの?」最近ではこういったご質問をよくいただきます。
よくありがちなのが、「とりあえずInstagramを始めてみよう」とか、「動画を作ろう」といった“手法先行”の取り組み。でもそれでは、なかなか成果につながりません。採用広報で重要なのは、“誰に、何を、どう伝えるか”を設計すること。いわゆる「コミュニケーション設計」から始める必要があります。
つまり、まずやるべきは「誰に来てほしいのか?」を明確にすること。その上で、「自社のどんな魅力がその人に刺さるのか?」「どんな伝え方をすれば共感を得られるか?」という視点で、切り口や伝達方法を練っていくべきなのです。
これは、広告におけるターゲティングやマーケティングの考え方と非常に似ています。求職者を“お客様”と捉え、自社への興味・関心を醸成していく——まさに採用広報は、採用マーケティングといっても過言ではありません。
2. 採用広報、失敗しないための3ステップ
では、実際にどのように採用広報を進めていけばいいのか?ここでは「失敗しないための3ステップ」をご紹介します。
ステップ①:ターゲットの明確化
まずやるべきは「誰に来てほしいか」を明確にすることです。
例えば「若手が足りない」と言っても、20代前半と後半では価値観も行動も異なりますし、理系か文系か、都心志向か地方志向かでもアプローチの仕方が変わってきます。
ターゲットを「ぼんやりした属性」ではなく、「具体的なペルソナ」に落とし込むことが成功の第一歩です。たとえば、「都内在住・25歳・大学卒・SNS活用頻度高め・社会貢献性のある仕事に興味あり」など。こうした情報をもとに、メッセージやチャネルを最適化していきます。
ステップ②:求職者の心に響く「切り口」の策定
次に重要なのが「何をどう伝えるか?」という“切り口”の設計です。
ここでポイントとなるのが、求職者が重視する「4つのP」。
- Philosophy(理念・目的):企業が何のために存在しているのか。Z世代を中心に、「共感できる理念」が企業選びの決め手になることも
- People(働く人):どんな人が、どんな思いで働いているのか。社員インタビューやエピソードが特に有効
- Profession(仕事・事業):事業内容ではなく、なぜその事業に取り組むのかという“物語”を語る
- Privilege(待遇・制度):「制度がある」だけでなく、「なぜ導入したか」「どう活用されているか」の背景が共感を呼ぶ
中でも、特に力を入れて発信したいのが「People(働く人)」です。
なぜなら、今の消費行動は「モノ消費」から「イミ消費」、そして「ヒト消費」へとシフトしてきているからです。誰が作ったか、どんな想いがあるのかに共感してモノを選ぶ——この傾向は採用にも当てはまります。
少し前までは「社会貢献性」や「環境への配慮」といった“意味”があるかどうかが重視されていましたが、今は「誰がやっているか」「どんな人がいるのか」が最大の関心事。推し活やYouTuber、インフルエンサーの台頭はその象徴です。
だからこそ、採用広報においても「人」にフォーカスした発信が効果を発揮します。「この先輩と働いてみたい」「この人の考え方に共感した」——そんな“人を軸とした共感”が、求職者の行動を後押ししてくれるのです。
社員インタビューや創業者ストーリー、開発者の苦労話など、背景にある“物語”を伝えることが、他社との差別化にもつながります。人を起点にしたストーリーテリングは、企業のリアルさと温度感を伝える最強の手段です。
ステップ③:伝える手法の設計(PESOモデル)
「何をどう伝えるか」が定まったら、次は「どこでどう伝えるか」のメディア設計です。
ここで活用したいのが、PESOモデルというフレームワーク。
- Paid(ペイドメディア):広告(Web広告、求人媒体、TVCMなど)
- Earned(アーンドメディア):メディア掲載、口コミ、レビューサイト
- Shared(シェアードメディア):SNSでの拡散や共感コンテンツ
- Owned(オウンドメディア):採用サイト、ブログ、メルマガなど
<メディアごとの具体活用例>
- ペイドメディア(広告)
- 求人媒体に加え、Instagram広告で「社員のリアルな働き方動画」を配信
- YouTubeショート広告で「1分でわかる当社の理念」動画を配信。ターゲット層への認知を促進
- アーンドメディア(口コミ・取材)
- 業界専門メディアへの寄稿で「働きやすい職場づくり」の取り組みを紹介。信頼性UP
- OpenWorkでの社員レビュー依頼とモニタリングを実施。改善点の把握と応募者対応の質向上に寄与
- 業界専門メディアへの寄稿で「働きやすい職場づくり」の取り組みを紹介。信頼性UP
- シェアードメディア(SNS)
- 社員のInstagram運用ルールを策定し、「#◯◯のある暮らし」といったハッシュタグで日常を投稿
- X(旧Twitter)での社員対談ライブ配信が好評。双方向コミュニケーションの入口に
- 社員のInstagram運用ルールを策定し、「#◯◯のある暮らし」といったハッシュタグで日常を投稿
- オウンドメディア
- 採用ブログで「社員インタビュー」「社内イベント」「職種紹介」「制度の背景」などを連載形式で更新
- noteで「創業ストーリー」「代表の想い」などの感情的価値を深掘り。CVR向上に貢献
重要なのは、何か一つに偏るのではなく、これらを複合的に組み合わせることです。求職者は、採用サイトを見ただけでは判断しません。「この企業、なんか良さそう」と思ったとき、今は必ず他のサイトで“答え合わせ”をしにいきます。
SNS、口コミ、ニュース記事——あらゆる情報源を横断して、自分なりに企業の全体像を掴もうとします。だからこそ、自社発信だけでなく、第三者による語りや、多様な情報接点を設けておくことが、安心感・信頼感につながるのです。
これはまさに、採用の「外堀を埋める」作業。情報が多く、かつそれが複数のメディアに分散して存在していることが、求職者の不安を取り除き、最終的に応募というアクションにつながります。
3. 採用広報の実践事例(業種別)
ここからは、実際に採用広報を取り入れて成果を上げた企業の事例をご紹介します。業種や規模によって課題も手法も異なりますが、共通しているのは「自社らしさをどう表現するか」「どのメディアをどう活用するか」といった点に向き合い、試行錯誤を重ねていることです。
採用広報は、派手なコンテンツを作れば成功するわけではありません。むしろ大切なのは、自社の価値や人の魅力をどう丁寧に伝えていくか。その意味でも、ここで紹介する事例は非常に参考になるはずです。
事例①:老舗製造業が「社員ストーリー」で若手応募が3倍に
創業80年を超える部品製造メーカーA社。技術力には定評があり、取引先も安定している一方で、「若手が全然来ない」という悩みを長年抱えていました。理由は明確で、採用ページが“硬く古臭い”印象だったからです。業務内容や製品情報は丁寧に載っているのに、「どんな人が、どんな想いで働いているのか」が一切伝わってこない。
そこでA社が取り組んだのが、「社員ストーリー」の導入でした。現場で働く若手社員へのインタビューを実施し、「入社の決め手」「仕事のやりがい」「職場の雰囲気」などを等身大の言葉で発信。文章もあえて“社外向けっぽさ”を出しすぎず、会話形式や本人の語り口を意識して構成しました。
さらに、制作した記事は採用サイトだけでなく、LinkedInやX(旧Twitter)などSNSでも発信。社内でも「〇〇さんの記事、読んだよ!」と話題になり、自然と社内の空気も前向きになっていきました。
結果、1年後の新卒エントリー数は前年の3倍に増加。応募者の面接時の志望動機にも「インタビュー記事で会社の雰囲気が伝わってきた」「この先輩と働いてみたいと思った」という声が多数見られました。
事例②:シリーズBのSaaS企業が「開発チームの裏側」を動画で発信
スタートアップSaaS企業B社は、シリーズBを終え急速な事業拡大フェーズに突入。しかしエンジニア採用が追いつかず、「プロダクトは評価されているのに、なぜ人が集まらないのか?」という課題に直面していました。
ヒアリングを進めて見えてきたのは、「企業の成長フェーズや技術レベルは魅力的なのに、外部にそれがまったく伝わっていない」という情報ギャップでした。採用サイトや求人票にはスペック情報は載っていても、“中で何が起きているのか”が見えてこなかったのです。
そこでB社が始めたのが、YouTubeを活用した「開発チームのリアル発信」。リードエンジニアが語る設計思想や、開発の進め方、チームでのコミュニケーション風景などをドキュメンタリー風に編集し、「雰囲気」と「技術の深さ」の両面が伝わる動画を公開しました。
動画はSNSを通じてじわじわと話題になり、エンジニア界隈での認知度がアップ。半年後にはWantedly経由での応募数が2倍に増え、特に「動画を見てカルチャーが良さそうだと思った」と語るミドル層の応募者が増加しました。
事例③:地方BtoB企業が「リアルな福利厚生紹介」で共働き世代に刺さる
地方の老舗建材メーカーC社では、地元では知名度があるものの、県外や都市圏からの応募はゼロに近い状況。特に共働き世代の中堅社員層を採用したいものの、「地方=不便」というイメージが先行して、なかなか響いていませんでした。
そこでC社が注目したのは、「制度」ではなく「リアルな暮らし」の情報発信。例えば、育児中の社員がどんな働き方をしているか、社内託児所の1日の様子、地元の教育環境や週末の過ごし方など、ライフスタイル全体を“暮らしの目線”で伝えるコンテンツを制作。
これらはオウンドメディアの記事だけでなく、Instagramで写真つき投稿として展開。「#地方移住」「#子育てしやすい街」などのハッシュタグも活用し、関心層に届くよう工夫しました。
結果的に、東京や大阪から「暮らしを重視したい」と考えるミドル世代の応募が増加。面接でも「働く環境だけでなく、生活全体がイメージできた」と高評価を得ました。
いかがでしょうか。
どの事例にも共通するのは、「企業の中の人」のリアルな姿や、日常の温度感をどう伝えるかに注力している点です。採用広報とは、単なるアピールではなく、“共感される物語をどう描くか”の勝負。自社らしさを見つめ直し、最適なチャネルで発信していくことで、確実に変化は起きていきます。
4.まとめ|“選ばれる会社”になるために、まずは一歩を踏み出そう
採用難の時代において、「人を集める」から「人に選ばれる」企業へと変わることは、すべての会社に共通した課題です。
そんな中で、“採用広報”は単なるPR活動ではなく、会社と求職者の「信頼関係を築く」ための大切な架け橋になります。
- 誰に、何を、どのように伝えるのか?
- 自社の魅力を、自分たちの言葉で語れているか?
- 外部から見たときに「ここで働く人の顔」が浮かぶか?
こうした視点で、ぜひ今日からでも取り組んでみてください。最初は一つの記事、一人の社員の紹介からで大丈夫です。積み重ねが、確かな採用力に変わっていきます。
私自身、20年にわたり様々な業界で広報を支援してきましたが、「自分たちの言葉で、未来の仲間に語りかける企業」は、どんな環境でも人を惹きつける力を持っています。それは、広告よりも、PRテクニックよりも強力です。
ぜひ、あなたの会社らしい“採用広報”を、今日から始めてみてください。
「自社でも採用広報に取り組んでみたい」と思った方へ
「何から始めて良いかわからない」「うちの業種でできるのか不安」などの声もよく聞きます。そんなときは、まず一度、経験者の意見を聞いてみるのがおすすめです。プラスカラーでは、企業ごとに合った採用広報の設計支援も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。




