COLUMN
社内広報の重要性と効果的な実施体制の築き方|社員の心に火を灯す秘訣とは
2025.8.25
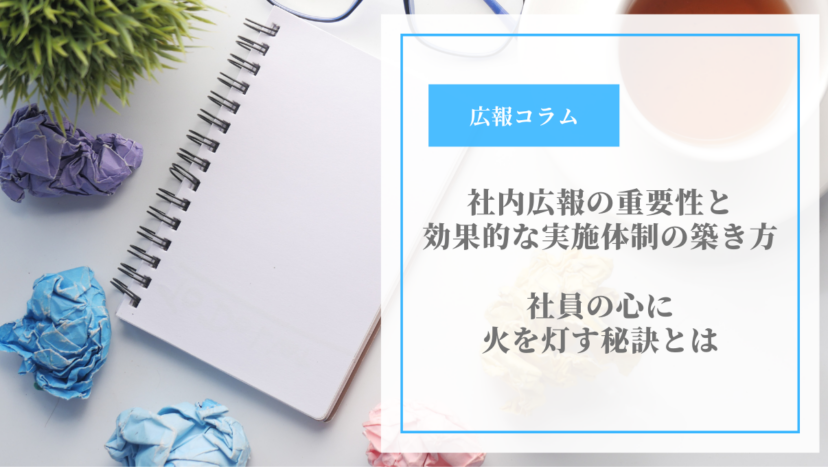
「うちの社員たち、本当に会社のことを理解しているのだろうか?」そう感じたことがある経営者や人事担当者の方は、少なくないはずです。近年、企業を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。多様な働き方の浸透、ジョブ型雇用の普及、Z世代の台頭、リモートワークの定着、DX化による業務改革——こうした動きの中で、社員一人ひとりが企業の方向性を理解し、自律的に行動できる組織づくりが求められています。 その鍵を握るのが、「社内広報」の力です。 社内広報とは、単に社内向けのお知らせを出す業務ではありません。経営と現場の橋渡しをし、社員の意識を揃え、エンゲージメントを高める——組織を内側から強くする戦略的なコミュニケーション活動なのです。しかし実際には、「会社の方針がよくわからない」「他部署の動きが見えず、孤立している気がする」「情報が一部の人にしか伝わっていない」 といった“社内の分断”が起きている企業も少なくありません。 多くの企業で「社内広報を強化しよう」「サポート体制をつくろう」という動きが加速しているいま、本記事では社内広報の基本から実践的な施策、体制構築のステップ、そして成功事例までを解説していきます。
目次
社内広報とは?目的と役割を整理する
まず、「社内広報とは何か?」を明確にしましょう。社外広報が“企業の顔”として外に向かって発信するのに対し、社内広報は“企業の心”を社員に伝えるものです。
社内広報の主な目的
- ビジョン・ミッション・バリューの浸透
企業がどこを目指し、何を大切にしているのか。理念が全社員に伝わることで、行動の軸が定まり、判断がブレなくなります。 - 社内コミュニケーションの活性化
「知っている」から「つながっている」へ。情報の共有を通じて、部門や役職を超えた関係性が生まれます。 - 部門間連携の強化
サイロ化を防ぎ、全社一丸となってプロジェクトに取り組む土壌をつくります。 - エンゲージメント向上と離職率の低下
会社への愛着や共感が高まれば、自然と定着率も上がります。 - イノベーションの促進
社内での情報共有が活発になることで、「あの部署で面白いことをやっているらしい」といった気づきが生まれ、化学反応が起こります。
つまり社内広報とは、「社員が企業を理解し、共感し、自ら行動したくなる」状態をつくるための、いわば“心のインフラ整備”なのです。
社内広報の具体的な施策とは?
社内広報と一口に言っても、手段は多岐にわたります。ここでは、特に活用しやすく効果の高い5つの施策をご紹介します。
① 社内報の発行
ポイント:コンテンツの“温度感”が命
社内報は、情報の定期的なまとめ役です。紙・PDF・イントラネットなど形式は多様ですが、重要なのは「社員が読みたくなる内容かどうか」。
たとえば、
- 経営者の想いを語るエッセイ
- 現場社員の奮闘を描くインタビュー
- 新入社員の紹介や働き方の変化
など、「共感」や「学び」が得られる内容にすると、社内に一体感が生まれます。実際、あるIT企業では、社内報に“お誕生日メッセージ”を添えるようにしたことで、閲覧率が2倍になったという例もあります。
② 社内イベント・朝会・タウンホールミーティング
ポイント:顔の見える場が、心理的安全性をつくる
「人は、顔の見える相手に心を開く」とよく言います。定期的な交流の場は、社内の信頼関係を深める土台です。ある企業では、月1回の「全社朝会」で、経営陣が直接現場の質問に答える時間を設けています。「会社の方向性が腹落ちした」「モヤモヤが晴れた」と社員からも好評です。
③ 社内SNS・グループウェアの活用
ポイント:双方向のコミュニケーションを当たり前に
SlackやTeams、LINE WORKSなどのツールを活用すれば、部署横断のやりとりが日常化します。「成功事例シェア」「お困り相談チャンネル」などの場を設けることで、自発的なやりとりが生まれやすくなります。
また、社内報の感想をポストする文化を育てれば、社内広報のPDCAも自然と回るようになります。
④ デジタル掲示板・イントラネットの整備
ポイント:「あの情報、どこにある?」をなくす
社内手続き、ガイドライン、福利厚生、イベント告知など、あらゆる情報の「ハブ」になるのがイントラネットです。ある製造業では「毎週月曜9時にイントラを確認する」文化を定着させたことで、社内ミスの件数が3割減少しました。更新頻度と分かりやすい設計がカギです。
⑤ 動画コンテンツの活用
ポイント:視覚と感情に訴えるメッセージの力
テキストでの発信に限界を感じている方は、動画の力を活用してみてください。
例えば、
- 経営者の新年メッセージ
- 部門紹介ムービー
- 新入社員向けのオンボーディング動画
など、言葉だけでは伝わらない“熱量”が届きます。スマホ撮影でも十分ですので、まずは気軽に始めてみるのがおすすめです。
社内広報の課題:なぜうまくいかないのか?
社内広報に取り組んでも、「思ったほど効果が出ない」「継続できない」と感じる企業は多いです。背景には、以下のような共通課題があります。
課題1:重要性の理解不足
「ただのお知らせ係でしょ?」
これは社内広報担当者がよく言われるセリフです。経営層や他部門が“戦略的広報”としての意義を理解していないと、予算もリソースも得られず、発信が形骸化してしまいます。
課題2:専任不在・兼任負荷
多くの企業では、人事や総務が“片手間”で社内広報を担っています。その結果、重要なコンテンツ制作が後回しになり、発信頻度が落ちてしまうのです。
課題3:情報収集の壁
「社内の動きが見えない」「情報が降りてこない」——これもよく聞く悩みです。担当者1人だけで全社の動きを把握するのは現実的ではありません。部門間の協力体制がカギを握ります。
課題4:効果測定が難しい
社外広報と違い、社内広報は数値的な評価がしづらい分野です。「誰が読んだのか」「どう変化したのか」が可視化されないと、改善も難しくなります。
社内広報を支えるための実施体制とは?
継続的かつ効果的な社内広報には、担当者だけに依存しない“組織全体の支援体制”が欠かせません。以下は、その基本ステップです。
ステップ1:経営層の理解と支援を得る
「情報発信は経営の責任でもある」——この意識を持ってもらうことがスタートです。経営層が自ら発信することで、社内の空気は大きく変わります。
ステップ2:部門横断の情報共有体制を構築
各部門に「広報窓口担当」を置き、定期的に情報提供を依頼する仕組みが有効です。ある企業では「広報ネタ会議」を月1で行い、他部門との連携が強まりました。
ステップ3:運用ルールとガイドラインの整備
「何を」「いつ」「どのように」発信するかを明文化することで、担当者が迷わずに動けます。
ステップ4:ツール・システムの導入
社内報作成ツール、アンケートシステム、イントラ更新支援など、デジタルの力を借りることで効率化と継続性が高まります。
ステップ5:貢献者への評価とインセンティブ設計
たとえば「広報ネタ提供賞」などを設け、関与してくれた社員を称えると、社内広報は“みんなでつくるもの”という認識に変わります。
社内広報サポートの実例紹介
事例①:A社(ITベンチャー)
- 経営者自らが社内報を一部執筆。社員の信頼を獲得
- Slackに「GOOD NEWS」チャンネルを設置し、成功体験を共有
- 広報と人事が社内報を共同運営し、月1で改善MTGを実施
結果、社員満足度調査で「経営方針の理解度」が前年比+35%に。
事例②:B社(老舗製造業)
- 各部門に情報提供者を配置し、月次でネタを収集
- 経営メッセージを動画化し、イントラで配信(再生回数:平均87%)
- 社内広報活動の貢献度を人事評価に反映
結果、離職率が前年比15%改善。若手社員の定着にもつながりました。
社内広報は“社員の心に火を灯す”活動
社内広報とは、社員一人ひとりの心に「自分もこの会社の一員だ」という灯をともす活動です。情報を届けるだけではなく、「共感を生む」「信頼を育む」「自発性を引き出す」ことが、本来の役割です。だからこそ、経営陣も現場も、全員で支える体制づくりが不可欠なのです。
おわりに:社内広報は未来の投資
短期的なKPIに直結しづらい社内広報。しかし、その“見えにくい価値”こそが、企業の未来を支えます。
- 経営理念が自然と語られるようになる
- 離職率が下がる
- 組織の一体感が増す
- 社内からイノベーションが生まれる
こうした成果は、すべて社内広報がもたらす“土壌”です。
今こそ、「伝える」から「つながる」へ。
御社の未来をつくる社内広報、まずは体制づくりから始めてみませんか?
自社に最適な社内広報の進め方を知りたい場合は・・・
プラスカラーでは、はじめての社内広報立ち上げや、既存施策の見直しも丁寧にサポートさせていただきます。
社内広報を「重要だ」と感じながらも、「何から始めればいいか分からない」「兼任で手が回らない」「発信しても反応が薄い」といったお悩みを抱えていませんか?もしそうであれば、まずは広報無料相談会にてご相談ください。
広報支援100社以上の広報コンサルタントが、貴社にとって最適な広報手法や改善施策をご提案いたします。




