COLUMN
PR戦略の立案方法|成果を出すためのステップと実践ポイント
2025.9.29
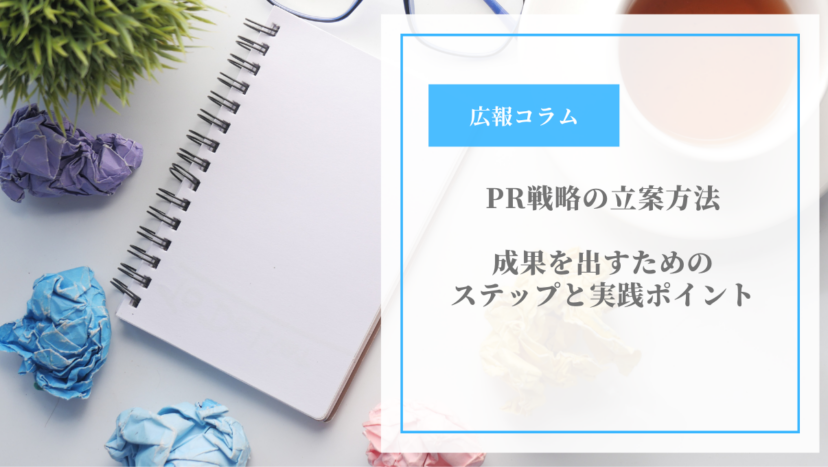
企業広報を取り巻く環境は、いま大きな転換期を迎えています。SNSやデジタルメディアの発達により、誰もが“発信者”となれる時代。ニュースが拡散するスピードは飛躍的に高まり、一方で誤解や炎上といったリスクも増しています。さらに近年は、Z世代を中心とした価値観の多様化、ESGやサステナビリティの重視、インターナルブランディングの重要性など、広報に求められる役割も広がっています。 こうした時代において、単発的な情報発信や場当たり的なメディア対応では、もはや成果は望めません。企業やブランドの「何を、誰に、どう伝えるか」を明確にし、全体を設計する“PR戦略”がますます重要になっています。実際、広報に携わる多くの方が「PR戦略の立て方がわからない」「計画はあるが実行につながっていない」といった課題を抱えているのではないでしょうか。 そこで本記事では、効果的なPR戦略の立て方をステップ形式で解説します。目的設定から現状分析、メッセージ設計、チャネル選定、そして社内を巻き込む実践方法まで、すぐに活かせる具体例を交えてお届けします。
目次
1. PR戦略とは?その役割と重要性
PR戦略とは何か?
PR戦略とは、「企業やブランドが伝えたいことを、誰に・どのように伝えるか」を明確にし、それをもとに行動計画を立てることを指します。戦略があることで、広報活動に軸が生まれ、情報発信にブレがなくなります。
なぜPR戦略が必要なのか?
たとえば、目の前の取材対応やSNS投稿に追われていると、短期的な対応ばかりになりがちです。すると、広報活動の“本来の目的”を見失いやすくなります。
PR戦略を立てることで、
- 広報活動の目的が明確になる
- 社内外との情報共有がスムーズになる
- 効果測定しやすくなる
といったメリットが生まれます。
2. PR戦略立案の基本ステップ
PR戦略は、単なる「広報計画」ではありません。企業やブランドの価値を最大限に伝えるための“設計図”です。ここでは、効果的なPR戦略を構築するためのステップを、実務的な視点でひとつひとつ解説していきます。
ステップ1:目的を明確にする ―「何のためのPRか?」
PR戦略は、「目的」から始まります。目的が曖昧なまま戦略を立ててしまうと、情報発信の方向性が定まらず、メディア対応やコンテンツ作成が場当たり的になります。
よくあるPR目的の例:
- 商品やサービスの認知度向上
- 企業ブランドの好感度アップ
- 社会的信頼の獲得(CSR・サステナビリティ活動の発信)
- 採用活動の支援(採用広報)
- リスク対策(危機管理広報)
- IPO準備やIR広報
目的が複数ある場合もありますが、「最も重視する1つ」を決めておくことが重要です。たとえば、「採用強化のために認知を広げたい」のであれば、「採用が主目的、認知は手段」という整理になります。
ステップ2:現状を分析する ―「今、どこに立っているか?」
目的が決まったら、次は「現状分析」です。ここでは内部と外部、両方の視点から状況を整理します。
内部分析(自社分析):
- これまでの広報活動の成果と課題(例:プレスリリースの掲載率、SNSのフォロワー数など)
- 経営戦略との整合性(企業の中期ビジョンや事業方針との連動)
- 自社の強み・弱み(製品力、専門性、PRリソースなど)
外部分析(市場・競合分析):
- 業界トレンド(例:DX、サステナビリティ、Z世代の価値観)
- 競合他社の広報動向(どのような媒体に露出しているか)
- メディアの関心事項(最近多い特集テーマや取材傾向)
<おすすめのフレームワーク>
| 分析手法 | 活用方法 |
|---|---|
| SWOT分析 | 自社の強み(Strength)・弱み(Weakness)、機会(Opportunity)・脅威(Threat)を整理 |
| PEST分析 | 外部環境(Politics, Economy, Society, Technology)を俯瞰 |
| 3C分析 | 顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)を比較して立ち位置を確認 |
ステップ3:ターゲットを明確にする ―「誰に伝えたいのか?」
PRは“誰に伝えるか”で大きく手法が変わります。ここでは「ターゲット層」を明確に設定します。
<具体的な分類例>
| セグメント | 想定ターゲット |
|---|---|
| 一般生活者 | SNS利用者、主婦、Z世代、シニア層など |
| ビジネス層 | 経営者、購買決裁者、同業他社 |
| メディア関係者 | 記者、編集者、業界インフルエンサー |
| 求職者 | 新卒、中途、地方在住者など |
より具体的な「ペルソナ設計(仮想の人物像)」を作っておくと、メッセージや媒体の選定もスムーズになります。
ステップ4:伝えるメッセージを設計する ―「何をどう伝えるか?」
次に、「伝える中身=メッセージ」を設計します。ここでは、ただ商品説明をするのではなく、「価値」や「社会的意義」を含んだメッセージにすることが大切です。
メッセージ設計のコツ:
- ターゲットの共感ポイントを意識する(例:「忙しい共働き世代に」「環境を考える学生に」)
- 数字やファクトを交える(例:「業界初」「満足度95%」)
- ストーリー性を持たせる(創業ストーリー、開発秘話など)
良い例:
「○○(自社製品)は、育児と仕事を両立するママたちの“毎日5分”を取り戻す、新しい家事アシスタントです」
ステップ5:チャネル(手段)を選ぶ ―「どこで伝えるか?」
メッセージが決まったら、それをどの媒体・チャネルを使って伝えるかを選定します。
<主なチャネル>
| チャネル | 活用例 |
|---|---|
| メディア露出 | プレスリリース配信、記者発表会、メディア向け説明会 |
| SNS・デジタル | X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、YouTube、note |
| オウンドメディア | 企業ブログ、採用ページ、ブランディングサイト |
| イベント・展示会 | 製品発表会、周年記念イベント、セミナー |
| スポンサー・共創企画 | 他社とのタイアップ、自治体との共同発表など |
目的やターゲットに応じて、チャネルを組み合わせて使う「クロスメディア戦略」も有効です。
ステップ6:実行スケジュールとリソースを整える ―「いつ、誰が動くのか?」
PR戦略は、計画だけで終わってはいけません。実行計画に落とし込み、実務として動ける形にします。
実行計画のポイント:
- 年間スケジュール・月次計画を立てる(PRカレンダーの作成)
- 外部リソース(PR会社、デザイン会社、ライターなど)の手配
- 社内関係者との情報共有(マーケ、開発、採用チームなど)
ステップ7:KPI・評価指標を設ける ―「効果をどう測るか?」
最後に、広報活動の効果を可視化する指標を設定します。KPI(重要業績評価指標)は目的によって異なります。
<目的別KPIの例>
| 目的 | 主なKPI |
|---|---|
| 認知度向上 | 記事掲載件数、PV数、SNSのリーチ数、検索数 |
| ブランド価値強化 | 好意度調査、ポジティブな言及の比率 |
| 採用支援 | 応募数、採用サイト訪問数、エントリー経路分析 |
| 危機対応 | ネガティブワードの減少、メディア対応件数 |
数値で測れるもの(定量)と、アンケート・感想などで測るもの(定性)の両方を組み合わせるのが理想です。
3. 【実践例】PR戦略を立てるシーン別の考え方
(1)新サービス立ち上げ時
- 目的:市場認知と初期ユーザー獲得
- ターゲット:IT業界、スタートアップ志向の若者
- メッセージ:「日常の不便をテクノロジーで解決」
- チャネル:テック系メディア、SNS広告、noteでの体験談記事
(2)採用広報
- 目的:企業文化や魅力の発信
- ターゲット:就活生、転職希望者
- メッセージ:「自由な社風で挑戦できる」
- チャネル:Wantedly、社員インタビュー記事、社長note
(3)企業の周年タイミング
- 目的:信頼性・歴史のアピール
- ターゲット:既存顧客、株主、メディア
- メッセージ:「○○年の歩みとこれからの挑戦」
- チャネル:記者会見、記念サイト、新聞広告
4. PR戦略を成功に導くためのポイント
一貫性と柔軟性の両立
どんなに優れた戦略も、時代や状況に応じてチューニングが必要です。「軸はブレない、手段は柔軟に」が広報の基本です。
社内理解を得る
広報は「社内広報」でもあります。経営陣や現場と定期的にコミュニケーションを取り、全社的な理解を得ることが大切です。
データと感覚の両立
「バズる」「拡散する」といった感覚も大切ですが、数字に基づいた検証をセットにしましょう。仮説 → 実行 → 検証 → 改善のサイクルを回します。
5. よくある失敗とその回避策
以下は、よくある失敗例とその回避策をまとめました。ぜひ参考にしてください。
| 失敗例 | 回避策 |
|---|---|
| 目的が曖昧なまま施策を開始 | 最初に「何を実現したいか」を明文化する |
| 詰め込みすぎの戦略 | 優先順位を明確にし、短期・中期で分ける |
| 一度決めた戦略を見直さない | 毎月・四半期で振り返りを実施する |
| 数字に偏りすぎて“想い”が伝わらない | 定量+定性的な評価でバランスをとる |
こちらの記事も参考になります。
▶失敗しない広報の始め方。成果を出すための広報戦略と実践ステップ
6. 社内を巻き込むPR戦略のコツ
広報の仕事というと、記者とのやりとりやSNS運用、メディア露出の企画など、いわゆる「社外向けの活動」を思い浮かべる方が多いかもしれません。けれど、実際に広報業務を進めていると、日々感じるのが「広報は社内との連携があってこそ成り立つ仕事」だということです。
例えば、製品の魅力を伝えるにも、社内の開発担当者や営業担当者のリアルな声がなければ、どこか薄っぺらい情報になってしまいます。逆に、現場の熱量や、社員一人ひとりのストーリーが加わることで、PRメッセージには深みと説得力が生まれます。
そこで今回は、私が20年間の広報経験の中で実践してきた「社内を巻き込むPR戦略のコツ」をご紹介します。社内に広報の理解者・協力者を増やし、チームで成果をあげていくためのヒントになれば幸いです。
成果を見える化して報告する
まず、社内の巻き込みを考えるうえで大事なのは「広報の成果を見える化すること」です。
というのも、広報の仕事はどうしても目に見えづらく、「何をやっているのかよく分からない」と思われがちです。だからこそ、広報の成果は積極的に社内へ発信していく必要があります。
たとえば、以下のような形で成果を共有してみてはいかがでしょうか。
- メディア掲載実績を画像付きで社内チャットに投稿
- アクセス数やSNSでの反響などをレポートにして、簡単なコメントを添えて報告
- 社内報で「広報が会社の印象をどう変えたか」のビフォーアフターを紹介
大切なのは、数字だけでなく「この結果を得るために、誰のどんな協力があったのか」を丁寧に伝えること。たとえば「○○部の△△さんのエピソードが記者の心に響き、今回の掲載につながりました」といった言葉があるだけで、関わった社員のモチベーションは大きく変わります。
報告は「成果の自慢」ではなく、「感謝と共有」の場。関係者にスポットライトを当てることで、「次も手伝いたい」と思ってもらえる空気が生まれます。
各部署にヒアリングを行い、ネタを収集する
PR活動の材料は、実は社内にたくさん眠っています。
「新しい技術を導入した」「お客様から感謝の声をいただいた」「新人が思い切った提案でプロジェクトを動かした」など、日常のなかにある“ちょっとした出来事”こそが、魅力的な広報ネタになることが少なくありません。
こうした情報を拾い上げるためには、各部署との日頃のコミュニケーションが不可欠です。
私がよくやっていたのは、「ネタ会」と呼んでいた月1回のヒアリングミーティング。営業、開発、バックオフィスなどの部門ごとに、最近起きた出来事や気づき、現場で感じたことなどをざっくばらんに話してもらう時間を設けていました。雑談のなかから、意外なエピソードが出てくることも多く、ネタの宝庫でした。
また、日頃から「これって広報に使えるかも?」と思ってもらえるよう、社内報やイントラで「こんな情報募集中です!」と呼びかけるのも効果的です。現場の“生”の情報は、広報が作るメッセージにリアリティと説得力を加えてくれます。
「ありがとう」を欠かさず伝える
これは当たり前のようでいて、意外と忘れがちなことかもしれません。
PR活動で社内の誰かに協力してもらったとき、たとえば取材に応じてくれた、情報提供をしてくれた、写真撮影に協力してくれた……そういった場面で「ありがとう」をしっかり伝えること。これは本当に大切です。
一言の感謝があるかないかで、相手の印象は大きく変わります。
私がよく使っていたのは、取材後に手書きのメッセージカードを渡したり、社内チャットで「本日の○○さんのご協力で、無事に撮影が終わりました!ありがとうございます」と投稿したりするやり方です。
小さな気配りが、次の協力につながります。広報の仕事は社内外の“共感”に支えられている――その意識を持つことが、長く続けていくうえでも大切な心構えとなります。
7. まとめ|地道な戦略こそがPRの力になる
PR戦略は、派手さよりも「地道な積み重ね」が鍵を握ります。短期で効果が見えづらいこともありますが、長期的に見ると戦略の有無は結果に大きく影響します。
私も最初のころは、目の前の業務に追われがちでした。しかし、時間をかけて戦略を練ることで、社内の信頼を得て、より大きな予算と裁量を持てるようになった経験があります。
もし「今さら戦略なんて…」と思っていたら、ぜひこの記事を参考に、小さな一歩から始めてみてくださいね。
広報は、企業の“人格”を伝える大切な役割。みなさんのPR戦略が、確かな成果に結びつくことを心から願っています。
「伝える」から「伝わる」へ。PR戦略を見直してみませんか?
PR戦略は、単に情報を出すための設計図ではありません。企業の本質を見つめ直し、「誰に・何を・どう届けるか」を明確にする、極めて重要な経営戦略のひとつです。
「PRの方向性に迷いがある」「社内の理解が得られず動けない」といった課題をお持ちでしたら、ぜひ一度ご相談ください。プロの視点で、貴社の魅力を“伝わるカタチ”に変えるお手伝いをいたします。




